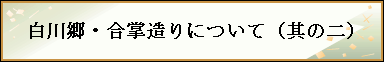この合掌造り民家はすでにブルーノ・タウト「日本の美の再発見」他、多くの専門家諸氏によって紹介され、構造はきわめて理論的で、世界各国を通じて全く独特のものであり、わが建築史上大切なる文化遺産であります。日本人の心のふるさとといった感があるこの貴重な合掌造り。
陽山亭の合掌造りは今からおよそ二百数十年前に造られたもので、建坪百数十坪・高さ四
十二尺余りの四階建てで、昭和四十八年十月まで岐阜県大野郡有家ヶ原に空(そら)友 茂氏の家族が住んでおりました。又商標の葉付き菊水の家紋は空氏より頂戴したものです。
「見聞諸家紋」には楠正成公の他、同族の和田氏や大芋氏が使用したとあります。
その後、昭和四十九年五月、白川郷より当地、埼玉県越生黒山に移築・復元する事ができました。解体された資材は、そのまま当地に復元するために、現地の職人さんの手で輸送・移築
しましたが、消防法・建築法により一部改装しました。
合掌造りは大部分が組み物で構成されていて、容易に解体・組立ができます。
といってもこれだけ巨大な木造建造物ですから、簡単ではありませんが、工法や技法的に粋を極めたものでなければ、このようなことはできません。
構造的にも実によく考えられていて、うまく力を分散させているので、再度、組み立てたときに障子や襖が、簡単に開閉できてしまい、飛騨の匠のすごさを実感いたしました。
下の写真は当時の移築行程を撮影したものですが、今となってはおそらく屋根の葺き替えをのぞいて、合掌造りの民家を建てているところを見ることはないでしょう。
また、残念ながら合掌造りの特徴である茅葺き屋根は、五年に一回ぐらい手入れをしていけば、十分もつものですが、移築十五年後に資材調達の困難や、火災の懸念より総葺替えを断念し、銅板にて覆いました。